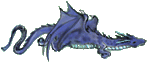 13 13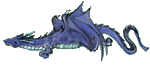 |
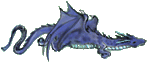 13 13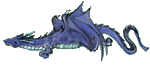 |
| 「間違いない。これは私の鱗の一部だ。」 「えっ?」 「そしてこのルビーのペンダントは、ガルドが常に身につけていたもの。」 「ガルドさんが?それがどうして僕の家に?」 考えてみればすぐに分かりそうなものだが、あまりに突然のことで、普段は冷静なルークもきょとんと目を見開くばかりであった。 「分からないか?父親の名を聞いてはいないのか?」 「知らないよ。父さんのことは母さんは何も教えてくれなかったから。このお守りだって、この間家を出る時に初めてもらったものだし・・・。」 「ふふふ・・・はははははっ。」 「ファイ?」 「初めて会った時からどこか懐かしいような気がしていたのだ。ガルドと同じ瞳をしていると思った。」 ルークは黙って竜の話に耳を傾けている。 「似ているはずだな。・・・・・・まさか、ガルドの忘れ形見に出会えるとは・・・・・・。」 「まさかっ!」 「そう、そのまさかだ。ルークはガルドの息子だ。」 「えっ?ガルドさんの?」 自分の父親に敬称をつけるのもおかしな話だが、いかんせん父親に出会ったことのないルークにとって、ガルドという名前はこのサファイア色の竜のパートナーである以外の何者でもなかった。 「これは天の導き、いや、ガルドの導きだな。よし、分かった。私がルークのパートナーになろう。ガルドの息子なら喜んで・・・。」 「本当?信じられないよ。」 ルークは想像もし得なかった展開に、頬をつねってみた。 「痛っ!本当だ。」 「ははは、ルークは面白いな。」 そんなルークの様子を見て、竜はおかしそうに尻尾を振った。 「そういえば、僕、ファイの本当の名前を聞いてなかったよね。というか、前に聞いたんだけど、うまく言えなくて・・・。結局ファイって呼ぶことになっちゃって・・・。」 頬を赤らめながら、ルークが言った。 「スターサファイアだ、ルーク。」 「スターサファイア?うわあ!ぴったりの名前だ。」 「この名前はガルドがつけてくれた。」 「ガルドさん・・・父さん・・・が?」 今まで何気なく口にしてきた”父さん”という言葉であったが、”ガルド”という立派な竜騎士が自分の父であるということに、ちょっぴり恥ずかしいような、それでいて嬉しいような不思議な気分だった。 顔も知らない自分の父親がつけたという名前であったが、もうこれ以外には考えられないほどぴったりな名前だと、ルークは思った。 「そうか。父さんも竜騎士だったんだ。何だか嬉しいな。僕も父さんみたいに立派な竜騎士になりたい。」 「ガルドはラスティア竜騎士隊で特選隊の隊長を務めていた。」 「と、特選隊!?」 ルークには驚きの連続だった。 特選隊といえば、入ることさえ難しいラスティア竜騎士隊の中でも、特に選ばれた10名。 自分の父親がその隊長を務めていたとは・・・。 「そのルビーは特選隊のメンバーのみが持つことを許されているものだ。そして、私とガルドは常に一心同体であるという証に、そのペンダントに私の鱗の一部を魔法で埋め込んだのだ。」 そういえばラスティア竜騎士特選隊は、身に付けている深紅の鎧から、別名ルビー竜騎士隊と呼ばれていた。 「スターサファイアと父さんは、それだけ固い絆で結ばれていたんだね。」 「ああ。しかし、これからは常にルークと一緒だ。」 「うん。」 「では、そろそろ行くか。新たな竜騎士誕生のために・・・。さあ、ルーク。私の背中に乗ってくれ。」 「改めて宜しくね、スターサファイア。」 こうしてルークとスターサファイアは、竜騎士ガルドとの不思議な絆により、最高のパートナーとなった。 力強く羽ばたくスターサファイアの背中で、ルークはいろいろなことを考えていた。 本当に短い間にいろいろなことがありすぎた。 しかしルークにとっては嬉しいことばかりだった。 スターサファイアとの再会、そして父親が竜騎士であったということ、スターサファイアのパートナーであったということ、更に竜騎士の中の竜騎士であったということ。 ルークにとって父親は、誰よりも自慢できる存在となった。 そして、これから何があっても竜騎士ギルや父親のように立派な竜騎士を目指していこうと、改めて決心した。 |
![]()